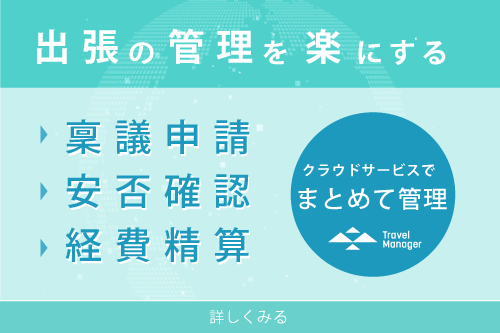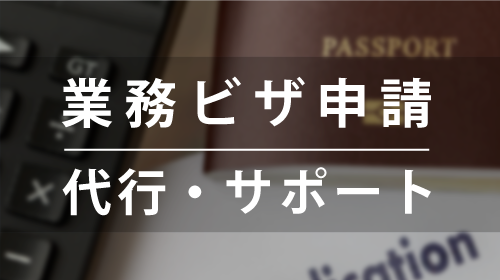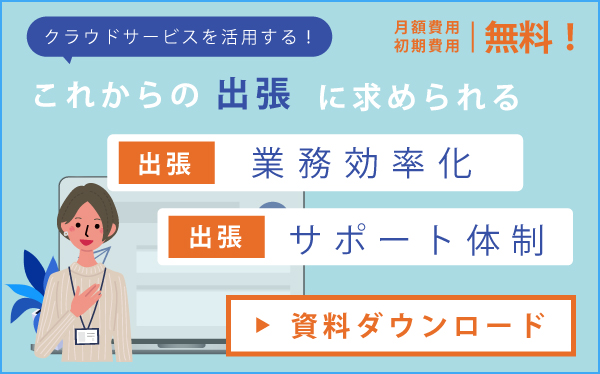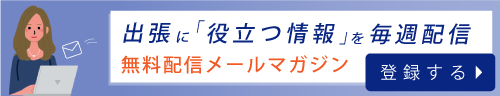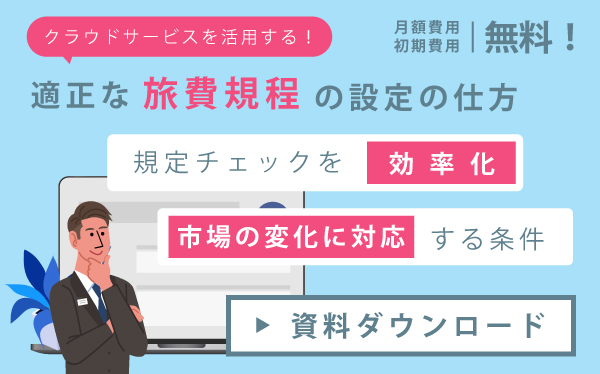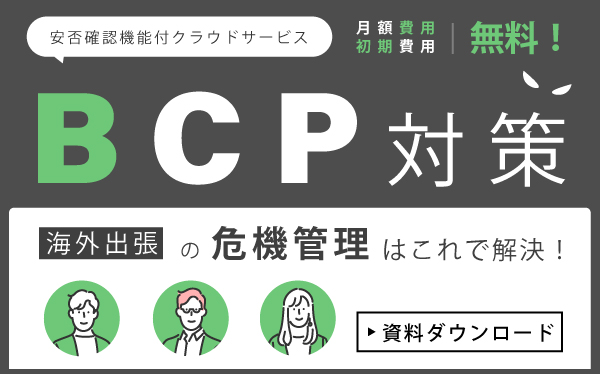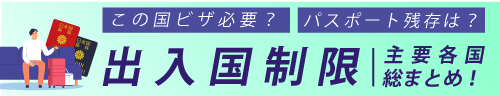観光とみなされる?海外出張費が税務調査で問題になる理由と正しい記録方法とは
海外出張は、企業のビジネス展開に欠かせない重要な活動です。
しかし、その出張費が「税務調査で問題になることがある」という点は、意外と見落とされがちです。
「本当に業務目的だったのか」
「観光とどう違うのか」
調査官の目は厳しく、場合によっては経費として認められないケースもあります。 これは、会社にとっても出張者本人にとっても、大きなリスクになりかねません。
本記事では、海外出張費が税務調査で問題になる理由や、チェックされる具体的なポイント、そして否認されないための備え方を、できるだけわかりやすく解説します。

目次
なぜ海外出張費は税務調査で問題になるのか?

海外出張にかかった費用は、当然ながら「業務に必要な経費」として処理されることがほとんどです。しかし、税務調査では、この当然に疑いの目が向けられることがあります。
というのも、出張の名目であっても、その内容によっては「実質的に観光や私的利用だった」と見なされてしまうことがあるためです。
特に海外出張は移動距離や費用が大きくなる分、税務署としても注目しやすい項目のひとつとなっています。
実際に、税務調査で「海外出張費の否認」を受けた企業の中には「何が問題だったのかわからなかった」と話すケースも少なくありません。
裏を返せば、必要な準備や記録さえあれば、本来は正しく経費として認められるはずのものだともいえます。
よくある否認事例とその共通点
実際の税務調査で海外出張費が否認されるケースには、共通する「見落としポイント」があります。 最初に多いのが「業務と観光が混在していた」ケースです。 例えば、週末を活用して高級ホテルに宿泊したり、観光地へ足を伸ばすための交通費を会社の経費に含めたりしていた場合、調査官に「業務目的かプライベート目的かわからない」と判断されやすく、否認につながります。 業務日数が50%以上であれば全額損金算入とされていますが、それ以下では按分処理が必要と明記されています。
大堀会計事務所 | 「観光を兼ねた海外出張費は、どこまで経費として認められる?」
納税協会 | 「納税協会ニュースweb用.indd」
次に、役員や社長に対して支給される日当や手当が、国家公務員の日当上限(3,800円程度)を大幅に超えるようなケースです。 宇都宮地裁では、代表者の日当が3,000円、取締役が2,000円のうち1,000円を超える部分を税務上の損金として認めず、否認した事例があります。 つまり、支給額が他社や公的基準と比べて「常識の範囲を超えている」場合、否認されやすいといえます。
TAX CONNECTION | 「【税務調査交渉及び、見落としがちな税務判断】日当の税務判断」
さらに、家族や知人を無条件に同行させ、その費用を経費計上してしまうケースもあります。 役員の配偶者や子どもを同伴し、その旅費を会社が負担していた場合は「業務に必要と認められない費用」として否認されることは明らかです。
北村税理士事務所 | 「法人税における海外渡航費の取扱いについて」
「業務目的でない」と判断されるパターンとは?
税務調査において、業務と私的な活動の区別が曖昧な場合、出張そのものが業務目的ではなかったと見なされるリスクがあります。
例えば「具体的な訪問先が記載されていない行程表」や「実際の打ち合わせ内容がわからない報告書」しか残っていない場合、調査官からは「本当に仕事だったのか?」と問われやすくなります。
また、現地で誰と会ったかがわからなかったり、打ち合わせの記録が一切なかったりする場合は「観光や個人的な旅行に過ぎないのでは」と判断されかねません。
実際の否認事例からもわかる通り、共通しているのは「業務であることを示す資料が不十分」や「支 出に合理的根拠がない」という点です。
こうした業務の証拠が不足していたことで、出張の目的そのものが否定されてしまったケースがあります。
逆に言えば、出張目的を明確化し、日当や旅費を説明できる根拠を用意し、私的利用分と区別しておくことができれば、正当な経費計上が可能ということです。
特に社長や役員が単独で海外出張をしている場合などは、形式的な資料だけではなく、誰に会い、何を話し、どういう成果があったのかを記録として残すことが重要です。
税務調査で見られる3つのチェックポイント

税務調査において調査官は、特定のポイントを重点的に確認します。 そのポイントは、大きく分けて3つあります。
これらはいずれも、業務の実態を確認するための視点です。
言い換えれば「本当に会社の事業活動の一環として行われた出張なのか」を、資料や状況証拠をもとにチェックされるということです。
出張のたびに詳細な準備をするのは大変かもしれませんが、あらかじめこの3つのポイントを意識しておくことで、万が一の税務調査にも慌てず対応できるようになります。
出張の目的が業務上かどうか
税務調査で最初に確認されるのが「その出張が本当に業務の一環として行われたものかどうか」です。 これは、出張費が経費として認められるうえで、最も基本的かつ重要なポイントといえます。
例えば、以下のような場合は、業務上の必要が明確であれば問題はありません。
新規取引先との打ち合わせ
現地法人の視察
展示会の出席
観光地に近い場所への出張
訪問先が実在するか不明
出張日数に対して予定が少なすぎる
特に気をつけたいのが「どこで・誰と・何をしたか」が曖昧なケースです。
行程表に「現地調査」や「関係先訪問」といった抽象的な記述だけでは、業務目的を説明するには不十分と判断されることがあります。
実際に出張が行われた証拠があるか
税務調査では、実際にその場所に行ったことを証明できるかどうかが問われます。
例えば、航空券の搭乗記録、ホテルの宿泊証明、現地での領収書、Wi-Fiの接続ログ、名刺交換の記録、訪問先とのメールなど、日常的に残る情報が証拠として役立ちます。
特に、会食の領収書や打ち合わせに関する議事メモなどが残っていれば、出張の実態を裏付ける材料として非常に有効です。
逆に、出張に行ったという主張があるだけで、渡航履歴や宿泊記録、打ち合わせの証跡などがまったく残っていない場合は、調査官から「本当に行ったのか?」と疑われる可能性があります。
場合によっては、経費全体が否認されてしまうリスクもあるため注意が必要です。
経費の金額や内訳が妥当かどうか
出張費が税務上の経費として認められるためには「その金額や内容が妥当であるかどうか」も大切なポイントです。
業務目的で出張したとしても、その費用が相場とかけ離れていたり、内容に不自然な点があれば、否認の対象になる可能性があります。
例えば、明らかに高級なホテルやビジネスクラスの航空券を利用していた場合、業務上の必要性を説明できる根拠が求められます。
また、支出の内訳が不明瞭で「何にいくら使ったか」がわからない場合も、調査官の疑念を招く要因になります。
さらに、役員など一部の社員にだけ高額な日当が支給されていたり、実費精算ではなく慣例で設定された手当が高すぎたりする場合も、注意が必要です。
事例でもお伝えした通り、過去には国家公務員の出張日当基準と比較され、過大と判断されたケースもあります。
否認されないために最低限やるべき準備

海外出張費が経費として認められるためには、出張そのものの妥当性を証明するだけでなく、「証拠の残し方」や「説明の仕方」も重要になります。
特に、税務調査では出張に関する書類の有無や内容が、そのまま調査結果に直結することがあります。
つまり、業務としての正当性があっても、証明できなければ否認される可能性があるということです。
裏を返せば、あらかじめ必要な情報を整理し、必要な資料をそろえておけば、調査の際にも自信をもって対応できます。
ここからは、「最低限これだけは準備しておきたい」という3つのポイントを取り上げ、具体的にどのような記録を残すべきか、どういった点に気をつけるべきかを解説していきます。
旅程表・訪問先との記録・報告書の残し方
出張の正当性を証明するうえで「記録を残しておくこと」が重要な訳ですが、特に重視すべきなのが「旅程表(スケジュール)・訪問先とのやりとり・出張後の報告書」です。
旅程表については、出張の出発日から帰着日まで、日ごとに「誰と・どこで・何をするか」まで記載しておくことが重要です。
例えば「午前10時〜A社にて商談/午後〜B展示会場を視察」といった形で、業務目的が伝わる内容になっていれば、調査官にとっても納得しやすくなります。
訪問先との記録としては、メールのやりとりやアポイントを取った証拠、名刺、商談メモなどが有効。
できればPDFや写真で保存し、後から確認できる状態にしておくと安心です。
さらに、出張後には簡単でもよいので報告書を作成しておくと、出張内容に一貫性が生まれ、税務署にも明確に説明できます。
報告書には「訪問先・目的・得られた成果・今後の対応」などを箇条書きでも構わないので記載しておくと良いでしょう。
こうした書類が揃っていれば、たとえ税務調査が入っても「業務のために行った正当な出張である」ことを自信をもって説明できます。
個人の観光や延泊との線引きをどう記録すべきか
海外出張では、現地での業務が終わった後に観光したり、土日を利用して延泊したりするケースも珍しくありません。
こうしたプライベートな行動自体は違法ではありませんが、税務上の経費として認められるかどうかは全く別の話です。
このリスクを避けるためには「どこまでが業務で、どこからが私的な活動か」をあらかじめ明確に分けて記録しておくことが大切。
例えば、旅程表に業務日程と延泊日程をきちんと分けて記載したり、領収書やホテルの予約情報を業務用・私用で分けて保管したりするなどの工夫が有効です。
また、延泊によって航空券の価格が下がるケースもありますが、その場合でも「延泊が業務と無関係であること」と「会社にとって損得がないこと」を説明できるようにしておくと安心です。
要するに「出張のついでに観光した」という構図は問題ではなく、それをどう記録し、どう区別するかが問われているということです。
事前に税理士と相談しておくべきこと
海外出張に関する経費処理は、現場の担当者の判断だけでは対応が難しい場面もあります。
特に「この支出は業務として妥当なのか」や「この資料で十分なのか」といった判断には、税務上の専門的な視点が欠かせません。
こうした場合に頼れるのが、顧問税理士の存在です。
出張前の段階で一度相談しておけば、どこまでを経費として計上できるのか、どんな証拠書類が必要なのかを具体的に教えてもらうことができます。例えば、曖昧になりがちな延泊費用の扱いや、現地での会食・交際費の処理についても、税理士から事前にアドバイスを受けておくことで、後々のトラブルを避けやすくなります。
また、税理士が関与していることで、税務調査の際に「会社としてルールに則って対応している」という姿勢を示すことにもつながります。
全ての出張で税理士に確認する必要はありませんが、判断に迷うようなケースが出てきたら、事前相談をルール化しておくと安心です。
IACEトラベルで実現できる安心の出張管理

ここまでご紹介してきたように、海外出張費が税務調査で否認されないためには、出張の目的や内容をしっかり記録し、証拠として残しておくことが欠かせません。
しかし、実際には出張のたびに旅程表を作成し、訪問先とのやりとりを整理し、領収書や書類を保管するのは、現場の担当者にとって大きな負担です。
そうした煩雑な業務をサポートしてくれるのが、IACEトラベルの法人向けクラウド出張手配サービス「Smart BTM」です。
Smart BTMでは、航空券やホテル、Wi-Fi、査証(ビザ)など、海外出張に必要な手配を全てオンラインで一元管理できます。
予約内容は自動的にデータとして記録され、出張者ごとのスケジュールや費用情報も蓄積されていくため、「誰が・いつ・どこへ・何のために出張したか」を後から確認することが可能です。
また、出張費は会社にまとめて請求されるため、立替精算が不要になります。
出張者にとっては手続きがシンプルになり、経理担当者にとっては「証憑がそろった状態」での処理ができるというメリットがあります。さらに、IACEトラベルでは24時間365日、日本人スタッフが対応するアシスタントサービスも提供しており、急なトラブルや変更にも柔軟に対応できます。
税務調査のリスクに備えながら、業務効率も高めていく。 その両立を目指すなら、Smart BTMは強力な選択肢となるはずです。
まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください。 現状の出張手配や経費処理の課題を共有いただければ、最適な導入方法をご提案いたします。
Smart BTMの特徴
- 初期費用と使用料が「無料」
- 出張者が個々に予約、費用は後払い一括請求
- 手配先の統一と出張データ(費用)の管理
- 24時間365日出張者をサポート
- チャット機能でメッセージの送受信