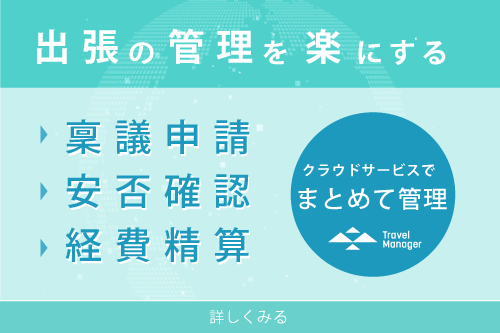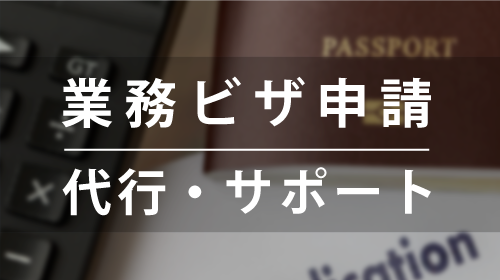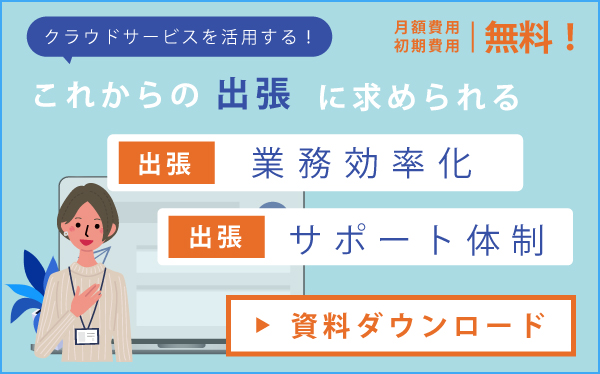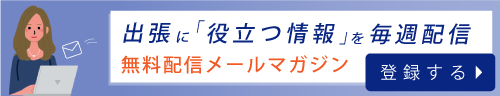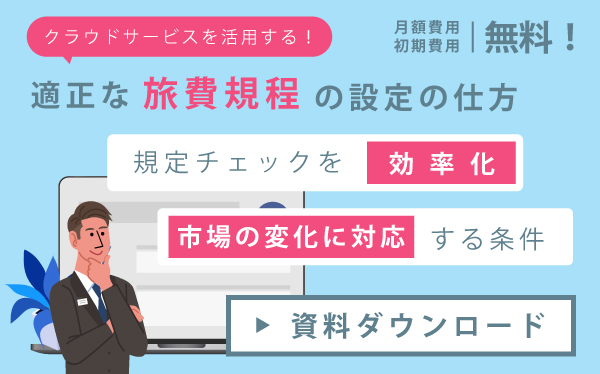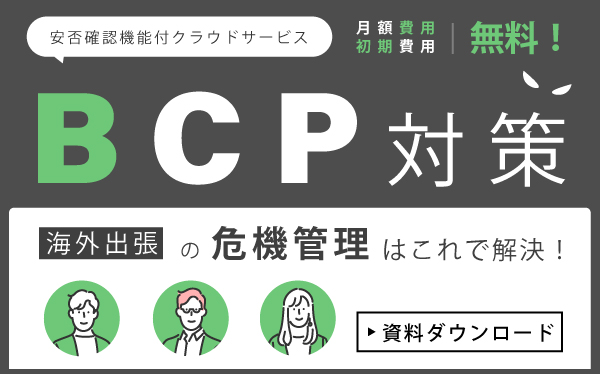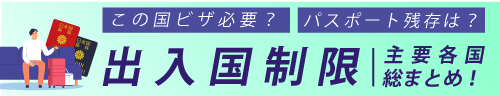【人事担当者向け】海外赴任の進め方
押さえるべき準備・制度・支援の基本
海外赴任が決まると、本人やご家族の準備が注目されがちですが、実務対応は、本人だけでなく「送り出す側」の人事・総務部門にも及びます。住居やビザの手配、現地での生活環境への配慮、健康面や教育面のサポート体制整備など、関係する領域は幅広く、業務が属人化しやすいのも現実です。 本コラムでは、初めて海外赴任を担当する方にも役立つように、出発前の準備から制度設計、現地支援、帰任対応まで、必要な知識と実務ポイントを時系列で整理しました。経験や属人的な対応に依存せず、次の対応にも活かせるしくみとして整備する際の参考資料としてご活用ください。

目次
駐在と赴任の違いを整理する

海外勤務とひと口に言っても、その形態は一様ではありません。特に「駐在」と「赴任」は似たように扱われがちですが、実際には目的や期間、待遇などに明確な違いがあります。まずはこの違いを整理することが、業務の計画や制度設計を進める上での第一歩となります。
派遣の目的と期間の違い
駐在は、現地法人や拠点の経営・運営に継続的に関わることを目的とした長期派遣を指します。企業の中長期戦略の一環として、数年単位での配置が想定され、家族帯同のケースも多く見られます。
一方、赴任はプロジェクト型や技術支援型など、特定の業務達成を目的とするケースが多く、任期も比較的短期間です。期間が明確に区切られており、成果と任務完了を前提とした派遣が一般的です。
給与・待遇・契約形態の整理
駐在員は本社側の給与体系に基づき、日本国内の給与をベースに各種手当(海外勤務手当、住宅補助、教育費など)が上乗せされる形が一般的です。生活基盤を現地に移すことから、企業側が包括的に支援を行う前提になっています。
一方で赴任者は、プロジェクトの性質や赴任地の条件に応じて契約内容が調整されることもあり、場合によっては給与水準や手当の考え方が異なる場合もあります。赴任形態によっては、出向契約や限定期間契約となることもあるため、制度面での確認は不可欠です。
ローカル採用との区別も押さえる
現地法人によって直接雇用される「ローカル採用」は、駐在・赴任とはまったく異なる制度です。雇用契約は現地法人との間で結ばれ、現地法に基づく給与体系・福利厚生が適用されます。
駐在や赴任は、あくまで日本本社の管理下にある出向または在籍出向という位置づけですが、ローカル採用はその対象外となります。管理や支援の範囲が大きく異なるため、人事制度上の区別は明確にしておく必要があります。
赴任が決まったら最初にすべきこと

海外赴任が正式に決まったら、人事や総務担当者は早急に「誰が・何を・どの順で進めるか」を整理する必要があります。初動を誤ると、以降の対応にしわ寄せが生じ、本人や帯同家族の不安も増してしまいます。まずは以下の3点を早い段階で押さえましょう。
家族の意向と帯同可否の確認
本人にとっても、家族にとっても、海外赴任は生活基盤の大きな変化を伴います。帯同が可能かどうか、帯同するなら学校や住環境はどうするか、単身赴任ならサポート体制をどう整えるか――早期のすり合わせが欠かせません。
特にお子さまがいる場合、日本の在籍校との調整や現地校・インター校の選定にも時間がかかるため、帯同可否は準備の起点として最初に確認しておくべき事項です。
初動時に確認すべき社内対応
社内で整っている制度や外部委託先の有無により、対応範囲は異なります。まずは以下のような点を洗い出し、漏れのない初動体制を整えましょう。
・ビザ申請の流れと担当部門(総務/庶務/外部提携先)
・健康診断や予防接種の実施要否とスケジュール
・帯同者向けの制度(住宅、教育手当、語学補助など)の有無
・赴任前の研修(異文化・安全・業務内容)の実施有無
・現地法人との連絡体制、責任者の明確化
制度が未整備の企業では、過去の赴任実績を洗い出して参考にしつつ、必要に応じて新たな基準を設けることも検討が必要です。
自社対応と外部委託の仕分け
すべてを社内で担おうとすると、業務が属人化しやすく、担当者に大きな負担がのしかかります。
たとえば以下のように、対応領域をあらかじめ仕分けしておくと、効率的な業務遂行につながります。
| 項目 | 社内対応 | 外部委託が可能な例 |
|---|---|---|
| ビザ・パスポート申請 | 一部社内 | 行政書士・旅行会社 |
| 引越・荷物手配 | 社内手配可能 | 海外引越専門業者 |
| 学校・医療機関の情報 | 限定的 | 現地コンサル・エージェント |
| メンタルヘルス支援 | 社内窓口設置 | 専門機関の活用 |
初動時に「自社でできること/外部に頼ること」の線引きを行い、役割分担とリードタイムを明確にしておくことが、全体進行の安定につながります。
出発までの準備スケジュール

海外赴任に向けた準備は、出発の3か月以上前から始めるのが理想です。ビザ取得や引越し手配、家族帯同に関する調整、健康診断など、対応すべき事項は多岐にわたり、想定よりも時間がかかることも珍しくありません。ここでは、時系列に沿って担当者が押さえておきたい準備項目を整理します。
3か月以上前に着手すべきこと
赴任者本人および帯同家族の健康診断・予防接種
特に6か月以上の赴任には、企業としての健康診断実施が法的義務となるケースもあります。予防接種は複数回の接種が必要な場合もあるため、早期着手が必須です。
パスポート確認とビザ申請準備
ビザの取得には国によって数週間〜数か月かかることもあります。必要書類の案内、申請代行業者の手配を含め、最初に着手すべき重要項目です。
住居・学校・帯同方針の整理
帯同する場合は、転校手続きや現地校の選定、日本の学校との調整も必要です。現地の住宅事情や家族構成をもとに、社宅利用や個別手配の可否も判断します。
1〜2か月前に整理する実務対応
航空券・ホテル・仮住まいの手配
現地の入居日まで時間が空く場合は、ホテルやマンスリーマンションの予約も含めた移行期間の計画が必要です。
引越荷物の仕分けと発送
航空便・船便・国内保管用などに分類して仕分けを行い、船便は目的地によっては2か月以上かかることもあるため、早めの引取手配が求められます。
国内住居の処理・車両の売却
賃貸住宅であれば契約解除通知、持ち家であればリロケーション(貸出)や留守宅管理サービスの検討も必要です。車両も名義変更・保険解約・輸送判断が発生します。
語学学習のスタート/現地情報の収集
赴任者・帯同者ともに語学対応が求められるケースが多いため、語学研修を含めた準備時間を確保しておくと安心です。
出発直前に行う最終確認
手荷物の準備とスーツケース梱包
到着後すぐに必要な物品(衣類・PC・医薬品・証明書類)は手荷物にまとめ、航空機への持込制限もあわせて確認しておきましょう。
公共インフラ・ライフラインの停止手続き
水道・電気・ガス・通信(Wi-Fi、携帯)などの契約停止/一時中断処理を忘れずに。必要に応じてあいさつ回りなども事前に調整します。
社内書類・承認フローの最終整理
出発報告や辞令の発令確認、海外赴任契約書類への署名など、社内プロセスを出発直前までにすべて完了させておく必要があります。
生活・文化・語学への備え

海外赴任の準備では、ビザや手続きといった制度面だけでなく、現地での暮らしや働き方への理解も欠かせません。赴任者やご家族が安心して新しい環境に馴染めるよう、あらかじめ生活インフラや文化的な違いを把握しておくことが大切です。特に語学や生活習慣への対応は、日々の小さなストレスを減らすうえでも有効です。
生活インフラと環境面の違いを知っておく
住宅の探し方や契約の習慣
地域によっては家具付き物件が一般的だったり、契約までに内見が必須だったりと、住宅の探し方ひとつとっても事情が異なります。安全性や生活利便性も含めて、現地法人や不動産会社と早めに相談しておくと安心です。
食事・医療・水道などの不安を解消するには
食事・医療・水道など、現地生活でよくある不安は事前に整理しておくと安心です。
たとえば、「日本食は手に入る?」「水は飲める?」「現地の病院は安心?」など、生活の基本に関わる不安を事前に想定し、必要な備えをしておくことがポイントです。
通信環境やネット規制もチェックを
インターネットが不安定な地域や、VPNが必要な国もあります。業務や生活に支障が出ないよう、現地情報をよく確認しておきましょう。
現地の文化や働き方に戸惑わないために
時間感覚や意思決定のスピード感
予定変更が多い、アポイントが曖昧、といった文化の違いに初めは驚くかもしれませんが、現地のリズムに合わせて柔軟に対応することが求められる場面もあります。
仕事の進め方や残業意識の違い
「言われていないことはやらない」「上司に報告せず完結する」など、日本とは前提が異なることも。すれ違いを避けるためにも、事前の共有やすり合わせが有効です。
安全に過ごすための事前対策
夜間の外出、タクシー利用、通勤ルートなど、地域によって注意が必要なポイントは異なります。現地法人からの情報共有や、行動ルールの明文化が役立ちます。
語学への対応は「完璧」より「安心」を
英語が通じにくい地域では、生活の中で現地語が必要になる場面が少なくありません。
とはいえ、完璧な語学力を目指す必要はなく、最低限のあいさつや買い物、病院での説明ができるだけでも、現地でのストレスはぐっと軽減されます。
最近では、赴任前に語学研修を用意したり、帯同家族向けのサポート制度を設けたりする企業も増えています。語学は「不安を減らす道具」として捉え、本人だけでなく家族全体で無理なく備える姿勢が大切です。
人事担当者が担う制度設計と費用管理

海外赴任に関わる制度や費用は、会社によって方針が異なりやすく、属人化や都度対応が発生しやすい分野です。 この項目では、人事・総務担当者が押さえておくべき基本設計の考え方を、3つの視点から整理します。
ビザ・保険・給与・住宅の設計方針
制度の整備状況は、赴任者が最も敏感に感じやすいポイントのひとつです。曖昧な部分が多いと混乱が生じやすく、出発までの負担も増えてしまいます。
ビザ取得と保険加入の管理範囲
ビザ申請は企業が一括管理するか、本人申請を支援する形にするか方針を決めておく必要があります。帯同家族を含めたスケジュール調整も忘れずに。保険については、現地での医療事情に応じた補償範囲(キャッシュレス診療、緊急搬送など)の選定が重要です。
給与体系と課税/社会保険の扱い
赴任中は本社基準の給与を維持するケースが多いですが、現地水準や物価の影響を加味した補正が必要になる場合もあります。年収構成や為替リスク、社会保険料の支払元(本社/本人)についても事前に整理が必要です。
住宅の提供・選定基準
社宅を用意するのか住宅手当を支給するのか、現地法人との連携範囲を明確にしておきます。地域に応じた安全性・通勤利便性・契約方法などを含め、上限金額や自己負担基準を定めておくと混乱を防げます。
手当・補助・費用負担の考え方
赴任者の家計や生活スタイルにも関わるのが、手当や補助制度の設計です。各企業で差が出やすいポイントでもあるため、事前に社内で整合をとっておくことが重要です。
赴任手当や物価補正手当
赴任地の物価や生活費に応じて定額支給する例が多く見られます。食費や光熱費の実費精算ではなく、シンプルな定額制を採用することで運用が安定します。
住宅補助・教育手当・帰国旅費の扱い
家族帯同時の住宅費補助、子どもの学費サポート、年1回の一時帰国旅費などは、生活安定や家族ケアの観点から重要な支援項目です。対象範囲・上限額・対象条件を明文化しておくとトラブルを防げます。
費用精算・通貨・為替のルール
外貨で支出される費用の精算時は、為替レートの基準(出発日/決済日など)を統一しておくとよいでしょう。領収書の取り扱いや証憑管理も、精算ガイドラインとして文書化しておくと運用しやすくなります。
現地支援と帰任まで見据えた計画
制度設計は「赴任直前まで」で完了ではありません。現地での生活中、そして帰任時にも管理すべき項目は続きます。担当者側で“出口までの流れ”を意識しておくことで、赴任業務の抜けや属人化を防ぐことができます。
現地支援体制の整備
赴任後も、現地法人や外部サポート会社と連携して「生活・医療・教育・安全」面の相談先を整備しておくと、赴任者の不安や孤立感を軽減できます。必要に応じて、メンタルヘルス支援や日本語対応窓口の活用も検討しましょう。
ビザ更新や帰任支援の想定
長期赴任では、現地でのビザ延長手続きや健康診断、出国準備などの対応が発生します。帰任後のポジション設計、住宅の再確保、学校転入の時期配慮なども、あらかじめ制度に組み込んでおけると理想です。
経験を次に活かす仕組み化
過去の赴任事例を蓄積し、テンプレートやFAQを整備しておくことで、次の赴任でもスムーズな対応が可能になります。担当者が変わっても運用が止まらない仕組みを意識することが、制度管理の質を高めるポイントです。
業務フローとマニュアルの整備

業務フローとマニュアルの整備
海外赴任業務は、担当者の経験や記憶に依存して進められることが多く、属人化しやすい領域です。まずは、出発までのタスクを時系列で整理し、業務フローとして可視化します。
そのうえで、申請書類や社内通知文、本人向け案内、外部依頼文書などのひな形を共通化し、フォルダ構成も含めて社内で一元管理できるようにします。運用が固定化していない項目については、想定ケースや判断基準も併記しておくと、次の担当者の判断負担を減らせます。
外部パートナーの選定と役割分担
ビザ申請、海外引越、住宅手配、医療保険、語学研修など、すべてを社内対応するのは現実的ではありません。業務ごとに委託可能な外部業者をリスト化し、契約条件や連絡先、依頼方法をマニュアルに記載しておくことで、毎回の確認作業を削減できます。
また、社内対応と外部委託の境界を明文化し、誰が判断・指示するかを明確にしておくことで、担当変更時の混乱や漏れを防ぐことができます。
メンタル・安全・生活支援の体制構築
赴任者や帯同家族の不安や孤立を防ぐため、出発前・現地到着後・赴任中の各フェーズで相談先を整理します。メンタルケアについては、外部カウンセリング窓口や保険会社付帯サービスの活用も検討対象とし、対象範囲や申込方法を明記しておきます。
治安や衛生面に不安のある地域では、行動ルールや避難時の対応先を文書化し、家族にも共有します。必要に応じて、現地法人や第三者機関と連携した安全情報の定期発信体制を整備します。
まとめ|再現性のある赴任管理へ

海外赴任業務は、対象者や赴任先によって条件が変わるため、毎回の対応がイレギュラーに見えがちです。しかし、基本となる制度設計・準備フロー・支援体制は、共通項として整理することができます。
まずは、社内で決定すべきルールや分担を明確にし、マニュアルやテンプレートを整備すること。次に、手続きや情報提供を担当者個人ではなくチームで支える運用に移行すること。そして、社内で完結しない領域については、早い段階で外部パートナーを選定し、役割と連携方法を共有しておくことが重要です。
海外赴任対応は、人事・総務部門にとっても“属人化を防ぎ、制度として定着させていく”べき領域です。一件ごとの負担を軽減しつつ、誰が担当しても一定の品質で回る体制を築くことが、結果的に赴任者と家族の安心につながります。
Smart BTMの特徴
- 初期費用と使用料が「無料」
- 出張者が個々に予約、費用は後払い一括請求
- 手配先の統一と出張データ(費用)の管理
- 24時間365日出張者をサポート
- チャット機能でメッセージの送受信