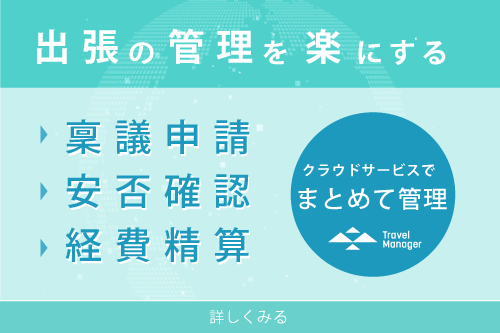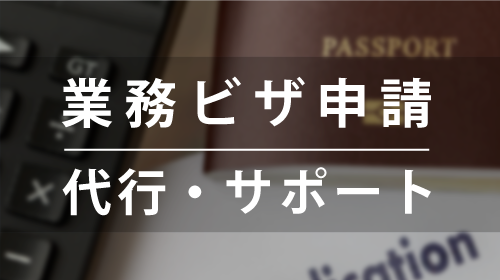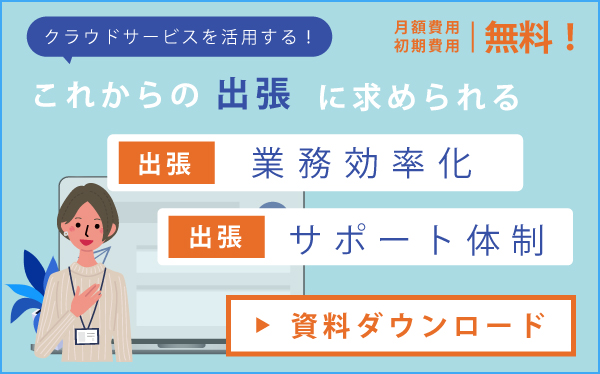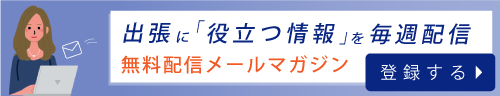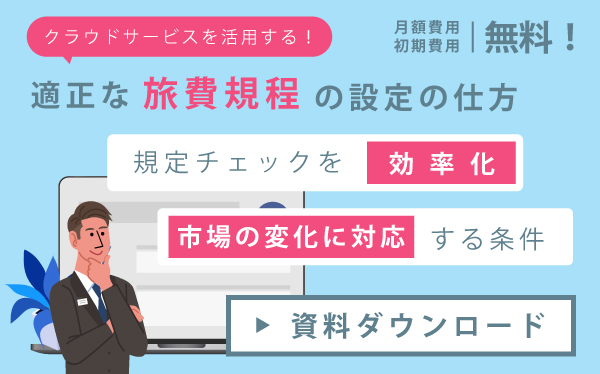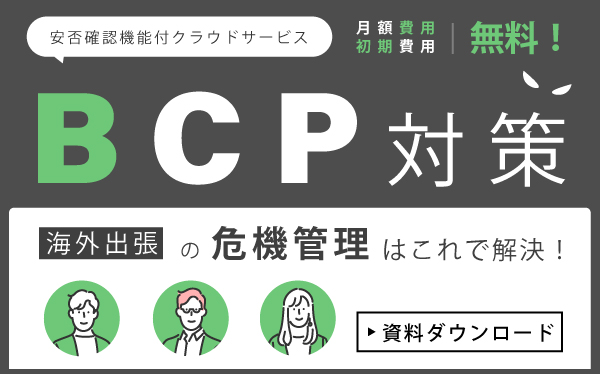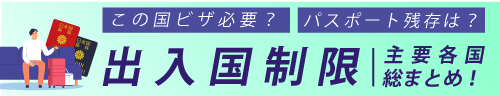海外視察でよく使われる移動手段まとめ|選び方と準備のポイント
海外視察では、現地でどう動くかを考えるのも大事なポイントです。
空港から市内までの移動、打ち合わせ先までの移動、都市をまたぐ移動まで、各場面ごとに選べる手段はいろいろあります。
タクシーや配車アプリ、地下鉄や鉄道、レンタカーなど、便利さもコストも国によってまちまちです。
選び方を間違えると時間を無駄にしたり、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。
この記事では、よく使われる移動手段をわかりやすく整理し、シーンに合わせた選び方のコツをご紹介します。
あわせて、視察をスムーズに進めるために欠かせない「事前準備」を効率化する方法もお伝えします。

海外視察でよく利用される移動手段

海外視察でよく利用される移動手段
海外視察で「どの移動手段を選ぶか」は、場面ごとに正解が変わります。
走る距離や時間帯、同行者の有無、荷物の量、現地の交通事情などで最適解が変わるため、事前に「場面別の選択肢」を押さえておくことが重要です。
以下では、よく使われる手段を一つずつ見ながら「いつ使うのが合理的か」や「どんな点に注意するか」を整理していきます。
タクシー・配車アプリ(Uber / Grab / DiDiなど)
現地での移動手段として、まず検討されるのがタクシーです。
空港から市内、ホテルから商談先など、目的地をピンポイントで指定できるため利便性が高く、荷物が多いときや時間に余裕がないときにも重宝します。
過去には、海外だと暴利な値段を吹っ掛けられることもありましたが、今は配車アプリを利用することで料金が事前に提示されるケースが多く、トラブルが防ぎやすくなっています。
都市によっては現地の定番アプリ(東南アジアのGrab、中国のDiDiなど)があるため、渡航前に確認しておくと安心です。
国や地域によってはタクシー料金の高さ、交通渋滞の激しさ、ドライバーの信頼性。 利用前に現地事情を調べ、自分のスケジュールや移動距離に合った形で使い分けると良いでしょう。
地下鉄・バス・鉄道などの公共交通機関
地下鉄やバス、鉄道といった公共交通機関は、コストを抑えつつ効率的に移動できる手段です。
特に大都市では路線網が発達しており、渋滞を避けて定刻どおりに移動できるメリットがあります。
一方で、乗り換えやチケット購入の方法が複雑なこともあり、慣れていないと戸惑う場面も少なくありません。
国や都市ごとに交通系ICカードやモバイルアプリが普及しているケースが多いため、事前に確認しておくとスムーズです。
公共交通は日中の移動や短距離移動に適しており、打ち合わせや視察先が駅やバス停の近くにある場合には特に有効です。
移動コストを抑えたいとき、渋滞のリスクを避けたいときに活用しやすい選択肢と言えるでしょう。
レンタカー
レンタカーは自由度が高く、自分のスケジュールに合わせて動ける手段です。 しかし、海外視察においては以下のようなデメリットが大きく、慎重に考える必要があります。
国際免許の取得が必要な地域が多い
交通ルールや道路事情が日本と大きく異なる
土地勘がない中での長距離移動は想定以上の時間がかかることもある
慣れない環境での運転はリスクが伴い、事故やトラブルに発生や、商談や視察のアポイントに遅れるケースも少なくありません。
安全性や効率性のことを考えると、レンタカーよりも専用車を利用した方が良いでしょう。
専用車
地下鉄やバス、鉄道といった公共交通機関は、コストを抑えつつ効率的に移動できる手段です。
特に大都市では路線網が発達しており、渋滞を避けて定刻どおりに移動できるメリットがあります。
一方で、乗り換えやチケット購入の方法が複雑なこともあり、慣れていないと戸惑う場面も少なくありません。
国や都市ごとに交通系ICカードやモバイルアプリが普及しているケースが多いため、事前に確認しておくとスムーズです。
公共交通は日中の移動や短距離移動に適しており、打ち合わせや視察先が駅やバス停の近くにある場合には特に有効です。
移動コストを抑えたいとき、渋滞のリスクを避けたいときに活用しやすい選択肢と言えるでしょう。
国内線フライトによる都市間移動
国土の広い国や複数都市を回る視察では、国内線フライトが欠かせない移動手段になります。
鉄道や車では時間がかかる距離でも、飛行機なら数時間で移動できるため、限られた日程のなかで効率的に訪問先を回ることが可能です。
ただし、空港の位置や移動時間、チェックイン手続きなどを考慮すると、実際にかかる時間は「飛行時間+α」になる点に注意が必要です。
また、便の遅延やキャンセルが比較的起こりやすいため、スケジュールには余裕を持たせておくのが安心です。
主要都市間を短期間で移動する必要がある場合や、鉄道や道路が発達していない地域に行く場合は、国内線フライトが最も合理的な選択肢となるでしょう。
移動手段を選ぶときの判断基準

海外視察は限られた時間のなかで成果を出さなければならないため、移動手段の選び方ひとつが大きな影響を与えます。
もし判断を誤れば、商談に遅れてしまったり、治安面で不安を感じたり、経費精算に手間がかかったりと、視察そのものの質を下げてしまうリスクがあります。
以下では、代表的な基準を挙げながら、それぞれの視点での考え方を紹介します。
効率性|スケジュールとの相性をどう見るか
海外視察では、限られた時間のなかで複数の訪問先を回るケースが多いため、移動にかかる時間がそのまま成果に直結します。
効率性を軽視してしまうと、予定していた商談や視察先に間に合わなかったり、移動に時間を取られて訪問件数が減ってしまうといった問題が起こります。
原因として多いのは、距離が短いからタクシーで十分と思ったものの現地特有の渋滞により予定が狂うケースや、鉄道やバスの本数が少なくて待ち時間が長引くケースです。
効率性を見極めるには、目的地までの所要時間・待ち時間・渋滞や混雑の可能性をあらかじめ調べ、スケジュールに組み込むことが大切です。
特に商談や会議の開始時間が決まっている場合は、多少コストが高くても「遅れにくい手段」を選ぶ方が結果的に得策です。
安全性|治安や時間帯のリスクを考慮するか
慣れない土地での移動では「安全に動けるかどうか」も大事な判断ポイントです。
日中は人も多く安心して利用できる公共交通でも、深夜になると運行が減り、治安の不安が増すこともあります。
よくある失敗は「料金が安いから」と夜中に公共交通を利用してしまい、想定外の場所で降りてしまったり、人気のないエリアを歩くことになってしまったりするケースです。
また、無認可のタクシーを利用して料金トラブルに巻き込まれることもあります。
そういった事態を避けるため、車両管理や保険が整った専用車を手配するのも手段のひとつです。 安全性を高められることから、企業視察では重宝されています。
利便性|言語やアプリの対応など加味するか
海外視察では、現地での移動に余計な手間をかけないことが重要です。
乗車券の買い方が分からず時間を取られる、タクシーで目的地を伝えられない、現金が必要なのに手元になくて慌てる。 こうした小さな不便が積み重なると、全体の行程に響いてしまいます。
利便性の観点で事前に確認しておきたいのは次のポイントです。
言語対応
配車アプリや地下鉄アプリが英語や日本語に対応しているか。
支払い方法
クレジットカードやアプリ決済が使えるか、それとも現金のみか。
チケット購入の手間
ICカードやモバイルチケットが利用できるか。
これらを把握しておけば、現地で迷う時間やストレスを最小限に抑えられます。 利便性を軽視すると「使えない」や「払えない」という状況になりかねないため、渡航前の下調べは必須です。
コスト|大まかな費用感と精算が簡単か
出張では移動そのものの費用だけでなく、経費を処理しやすいかどうかも大切です。
料金が安いからと選んだ手段が、領収書が発行されずに精算に手間取る…というのはよくある失敗例。 結果的に出張者も経理担当も余計な負担を抱えることになります。
また、国や都市によって「高くても便利」や「安いが不便」といった傾向が異なるため、おおまかな物価水準を事前に把握しておくことが重要です。
例えば、東南アジアではタクシーや配車アプリが安価に使える一方、欧米の大都市では公共交通を使った方がコストを抑えられる場合が多くあります。
つまり、渡航前には「移動にかかる費用感」と「領収書や明細の有無」を確認しておくことがポイントです。
コストは単なる金額の比較ではなく、後々の精算業務まで含めて総合的に効率的かどうかを基準に考えるべきなのです。
人数|あなただけなのか複数人なのか
移動手段を考えるときに意外と見落とされがちなのが「何人で移動するのか」という視点です。 人数や同行者の属性によって、最適な手段は大きく変わります。
例えば、一人での出張なら、地下鉄や配車アプリを使って柔軟に動くのが効率的です。
しかし、複数人で同じ場所に向かうなら、タクシー1台や専用車を手配した方が、待ち合わせや精算の手間も減らせます。
さらに、大人数の場合は、バンやマイクロバスといった車両を利用しないと、全員が一緒に移動するのは難しいでしょう。
また、同行者が社内の上司や取引先の場合は「安全性や快適さを優先した選択」が求められる場面もあります。
誰と何人で動くのかを踏まえて移動手段を決めることが、トラブルを避けつつスムーズな視察につながります。
地域ごとの移動事情とおすすめ手段

移動手段について整理してきましたが「結局はどうすればいいの?」と思うことでしょう。
答えはシンプルで「訪れる地域ごとの事情に合わせて使い分ける」です。 なぜなら、都市の交通インフラや物価水準、治安、移動距離の感覚がそれぞれ違うからです。
ここでは、代表的な地域ごとに移動事情を整理し、どんな選択肢が合理的なのかを紹介します。
あなたの渡航先に合わせてイメージを掴み、渡航前から安心して計画を立てられる準備を整えましょう。
アジア圏|安価で便利な配車アプリ、ただし渋滞に注意
アジアの主要都市では、タクシーや配車アプリが非常に手軽で安価に利用できます。
Grab(グラブ)やDiDi(ディディ)といったアプリを事前に入れておけば、言語の壁も比較的少なく、現地で迷わず移動できるのが大きなメリットです。
一方で、多くの都市では交通渋滞が深刻です。 距離が短くても移動に時間がかかることがあるため、商談や打ち合わせに合わせたスケジュール管理が欠かせません。
また、公共交通機関が整備されている都市では、鉄道や地下鉄を組み合わせた方が効率的に動けるケースもあります。
費用の安さに惹かれてタクシーや配車アプリだけに頼ると、渋滞で予定が崩れることもあるので、渡航前に現地の交通事情を調べ、場面に応じて使い分けるのが賢明です。
欧州|鉄道網が発達、都市間移動は鉄道が効率的
欧州は鉄道網が非常に発達しており、都市間の移動では鉄道が第一候補になります。
新幹線のような高速鉄道が主要都市を結んでおり、飛行機を利用するよりも短時間で移動できるケースも少なくありません。
駅は市街地に近い場所にあることが多く、空港までの移動や搭乗手続きに時間を取られない点も大きな魅力です。
都市内の移動でも地下鉄やトラムが整備されており、観光客やビジネス客にとって使いやすい環境が整っています。
ただし国や都市によって運行状況や治安の差があるため、利用する時間帯やエリアはあらかじめ確認しておくと安心です。
欧州では「都市間は鉄道で都市内は地下鉄やトラム」と押さえておけば、効率的かつ安心して動けるでしょう。
北米|距離が長く、飛行機+レンタカーの組み合わせが一般的
北米は国土が広大で、都市と都市の間が数百キロ単位で離れていることも珍しくありません。 そのため、都市間の移動は飛行機が基本です。
一方で、空港から市内や郊外の視察先へ向かう場合にはレンタカーがよく利用されます。
公共交通が十分に整備されていない地域も多く、特に工業団地や郊外の施設を訪れる際には車での移動が欠かせません。
同行者が複数人いる場合は、車1台をシェアすることで効率的に動けるのも利点です。
ただし、運転には国際免許証が必要となる場合があり、交通ルールや保険の内容も国ごとに異なるため、事前の確認は必須です。
北米では「都市間は飛行機、現地は車」と考えるのが現実的な選択肢といえるでしょう。
移動手段の他にも出張準備でやることは山ほどある

現地での移動を考える前に、渡航そのものに必要な手配が数多くあります。
航空券やホテルの予約、Wi-Fiの確保、査証の申請、保険の加入など、準備すべき項目は非常に多岐にわたります。
これらを個別に手配していると、管理が煩雑になるだけでなく、予定の重複や抜け漏れといったリスクが生じやすくなります。また、こうした手配に追われることで、本来の業務に集中しづらくなるのも実情です。
そこで近年注目されているのが、航空券やホテルはもちろん、通訳やガイドの手配も含めて旅行代理店に一括で相談し、出張全体を包括的にサポートする BTM(Business
Travel Management) という考え方です。
このBTMサービスを導入する企業は年々増えており、あらかじめ契約している旅行代理店があれば、出張の計画から手配、精算、実績管理に至るまで、一連の業務を一元的に管理することが可能になります。
まとめ

海外視察では、現地での移動手段をどう選ぶかが成果に直結します。
どの方法にもメリットとデメリットがあるため、スケジュールや人数、移動の目的に合わせて最適なものを選びましょう。
現地での移動は、専用車チャーターやアシスタント帯同を取り入れることで、安全性と効率性を大きく高められます。 Smart
BTMを活用すれば、そういった渡航準備を効率的に整えられるため、出張者は現地での活動に力を注げます。
現地移動は自分に合った方法を選び、基盤となる出張準備はSmart BTMに任せる。 このバランスが、海外視察を成功させるカギとなるでしょう。
IACEトラベルが提供する Smart BTM
を利用は、航空券やホテルの手配はオンラインでスムーズに完了し、送迎やガイドのアレンジはチャットで気軽に依頼できます。さらに、専任スタッフによるチャットや電話でのサポートがあり、急な相談にも柔軟に対応。24時間365日のサポート体制が整っているため、初めて訪れる国や不慣れな地域でも、安心して出張を進めることができます。
あわせて読みたいコラム
Smart BTMの特徴
- 初期費用と使用料が「無料」
- 出張者が個々に予約、費用は後払い一括請求
- 手配先の統一と出張データ(費用)の管理
- 24時間365日出張者をサポート
- チャット機能でメッセージの送受信